【急患対応】お急ぎの方は048-934-9804まで!
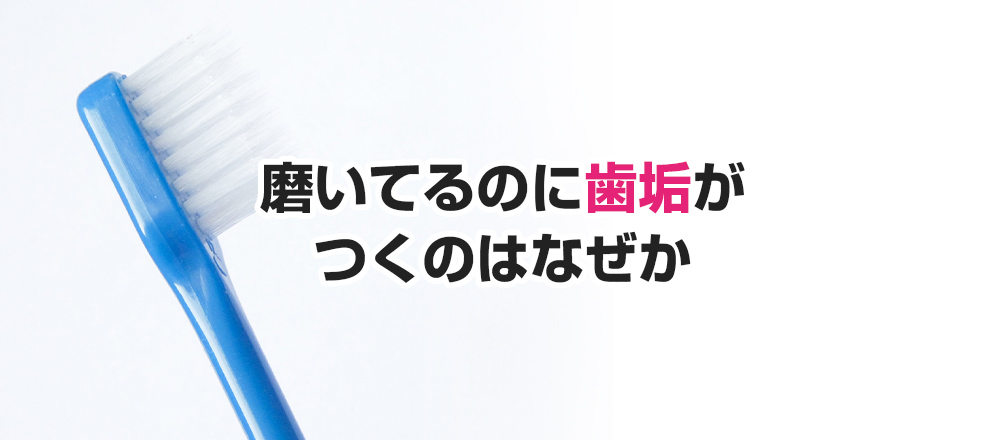
朝起きた時、歯の表面を舌で触るとヌメヌメとしていますよね。せっかく就寝前にしっかりと歯磨きをしたのに、朝になったら歯垢が再発している。
そんな現象を不思議に思う人も沢山いらっしゃるかと思います。ここでは、歯磨きをしても歯垢が再び付着してしまうメカニズムについて詳しく解説します。
歯のヌメヌメは歯垢だけではない?
まず始めに、歯の表面をヌメヌメとさせているのは、歯垢だけではないということを知っておいてください。私たちの歯は、正常な状態でヌメヌメとした被膜が形成されています。これを専門的には「ペリクル」と呼んでいます。
ペリクルは、唾液中の糖タンパク質がエナメル質に吸着されることで形成される被膜で、誰の歯にも存在しています。
被膜を形成することで歯を外来刺激から守る

歯の最表面を構成しているエナメル質はとても硬い組織ですが、酸性の刺激や機械的刺激に弱い性質を持っています。例えば、虫歯菌が産生する酸によって、エナメル質は徐々に溶けていきます。
あるいは、歯ブラシによるブラッシングのような機械的刺激が加わることでも、その圧力が強ければ簡単に傷ついてしまうことがあるのです。ペリクルはそうした刺激から歯質を守る役割を担っています。
ペリクルは除去しても数分で形成が始まる
しっかりと歯磨きをした後は、歯垢だけでなくペリクルも除去されます。けれどもペリクルは数分もしないうちに、再び形成が始まるのです。つまり、歯の表面は少なくともペリクルという被膜で常に覆われているということができます。
そしてこのペリクルは、歯質を保護するというメリットだけでなく、歯垢形成の起点になるというデメリットも持ち合わせていますので注意が必要です。
歯垢の原因である虫歯菌は完全に除去することはできない
歯垢には、1グラムあたり100億以上の細菌が含まれています。この細菌は、歯垢を除去することによって一時的に排除することは可能です。けれども、歯垢の中以外でも、口腔内全体には無数の虫歯菌は生息しています。これらの細菌を完全に除去し、口腔内を無菌化することは不可能です。
つまり、歯磨きをしたとしても、歯面に付着した一部の細菌を除去できるだけで、依然として口腔内には無数の虫歯菌が残っているとお考えください。そしてこれらの細菌は、きっかけさえあればすぐに歯垢の形成を始めることができるのです。
すぐに歯垢が付着する人の特徴

歯の表面にはペリクルという歯垢形成の足場があり、口腔内には無数の細菌が生息していますので、あとは材料さえそろえば歯垢の形成が始まります。
ここでは、その材料となり得るものについて、実際の食品や生活習慣などを詳しく解説します。
間食の習慣がある人
歯垢形成の主な原因は、食品に含まれる糖質です。3度の食後にきちんと歯磨きを行っていても、間食を摂っていたら、容易に歯垢は形成されます。特に間食というのは、糖質が多く含まれる食品が多いので、あっという間に歯垢が形成されていきます。
ちなみに、食品に含まれる糖質は虫歯菌の活動を活発にし、歯垢形成を促すだけでなく、酸の産生も促進しますので、虫歯も進行していきます。
磨き残しが多い人
どんなに歯磨きが上手な人でも歯列のどこかには、磨き残しがあるものです。そうして残った食べカスが歯垢の形成に寄与することは珍しくありません。
特に普段から磨き残しが多い人は、歯磨きをした後でも再び歯垢が形成されてしまうものです。
歯面に残りやすい食品を好んで食べている人
私たちの口腔内には、唾液による自浄作用というものが働いています。自浄作用とは、食後に残留した食べかすや不十分なブラッシングによる磨き残しがあったとしても、唾液によって徐々に取り除かれている現象です。
ただ、自浄作用が働きにくい食品を好んで食べていると、自ずと残留物が増えてきます。具体的には粘着性の高いキャラメルやお餅などは、歯面に残りやすい食品といえます。これらが残留していると、歯垢形成のきっかけとなりますので要注意です。
歯の表面が傷ついている人
どんなものでも表面に凹凸があると、汚れがたまりやすくないですか?これは歯も同じです。エナメル質の表面に傷がついていると、歯垢がたまりやすいような凹凸が形成されていますので、歯磨きをした後でも比較的短期間で歯垢の再生が始まります。ちなみにその傷というのは、肉眼で見える大きなものだけでなく、極めて微細な傷も含まれます。
私たちの歯には、意外に沢山の傷がついていますので、歯垢がたまりやすい傾向にある人は、それだけ傷が多いのかもしれません。
鼻ではなく口で呼吸をしている人
本来、私たち人間は鼻で呼吸をするのが適切な状態です。もちろん、口で呼吸をすることもありますが、それは激しい運動をした時に息が切れたり、風邪などで鼻が詰まったりした時に限られます。ただ、習慣的に口呼吸をしている人も珍しくはありません。
例えば出っ歯などの歯列不正の影響で、常に口が開いた状態では、口呼吸をせざるを得なくなります。そうすると、口腔内が乾燥してしまうので、風邪をひきやすくなるだけでなく、虫歯菌の活動も活性化されていってしまうのです。
なぜなら、口腔内が唾液で潤っていれば、自浄作用が働いて細菌の増殖なども抑制されるからです。そのため歯科では、できるだけ口呼吸を避けるよう指導する場面が多いといえます。
まとめ
このように、歯磨きをしているのに歯垢がついてしまうのは、何ら不思議なことではありません。私たちのお口の中には、常在菌と呼ばれる細菌が生息し、それらを完全に除去することは不可能だからです。それに加えて、上述したような歯垢が付きやすい特徴というものが存在しますので、該当する人は要注意です。
逆にいえば、これらの注意点を頭に入れて生活習慣を見直すことで、歯垢の形成を限りなく少なくすることは可能といえます。歯垢の形成を抑制できれば、虫歯菌の増殖を抑えられるだけでなく、歯石の形成まで防ぐことができるため、歯種病予防にもつながりますので、非常に有意義であるといえるでしょう。

